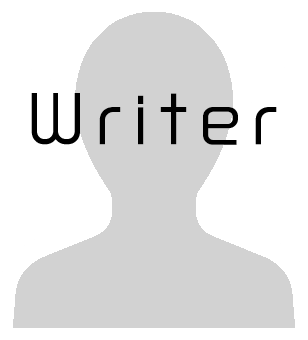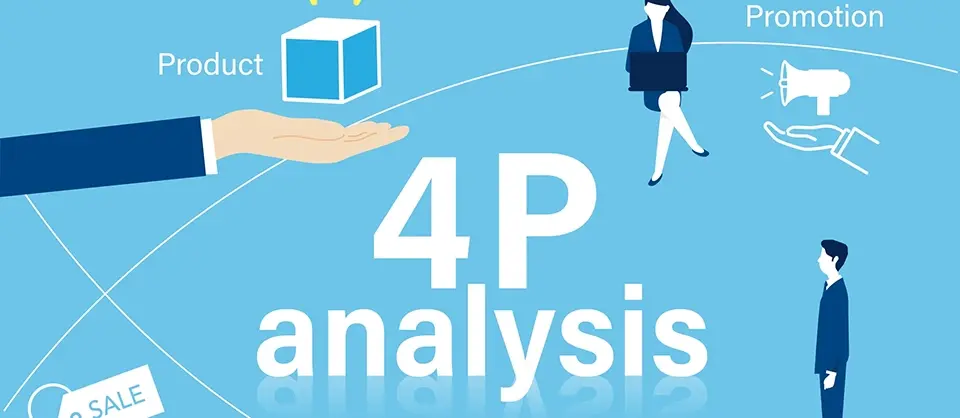マーケティングの新たな定義とは?歴史や分析手法、活動の流れもわかりやすく解説
公開日:

マーケティングは時代の移り変わりに伴って多様化します。定義に関しても、従来のものでは時代に対応できなくなっているため、新たな定義が生まれました。マーケティングの新たな定義とはどのようなものを指すのでしょうか。今回は、マーケティングの新たな定義と歴史や分析手法、活動の流れについて解説します。
マーケティングの定義
マーケティングの定義とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、公益社団法人日本マーケティング協会が1990年に制定した従来の定義と、2024年に刷新した新たな定義について解説します。
従来の定義
従来のマーケティングは、製品やサービスを売るための活動や戦略とされてきました。企業側が主体となり、売れるための仕組みづくりを考えて、市場をつくるために行動するのが当たり前でした。
新たな定義(2024年)
モノ消費からコト消費を重視する時代へと移行するなかで、マーケティングの新たな定義が提唱されています。
公益社団法人日本マーケティング協会によると、マーケティングとは「顧客や社会とともに価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセス」としています。
従来は企業主導型でしたが、新たな定義では顧客や社会全体を巻き込むことが前提となっているのが特徴です。利害関係者との関係性を構築しながら、市場を創造することを目的としています。
また、体験や経験に価値を見出す消費者が増えることで、コト消費を重視する傾向が強まっています。顧客や社会との関係づくりを大切にし、一緒になって価値を創造することがマーケティングの新たな考え方です。
出典:公益社団法人 日本マーケティング協会「34年振りにマーケティングの定義を刷新」
https://www.jma-jp.org/info/news/916-marketing

マーケティングの歴史
「マーケティング」という概念が誕生したのは、1900年代といわれています。アメリカのフォード社が最初に取り組んだことが発端です。ただし、日本では江戸時代に始まったという説もあります。安ければ売れる時代のなかで、フォード社はT型フォードを低価格で販売し、大衆車として世界に普及させました。
ここからは、アメリカの経営学者であるフィリップ・コトラーが提唱した「マーケティング1.0~5.0」をもとに、マーケティングの歴史を解説します。
より詳しく知りたい方は下記の記事も合わせてご覧ください。
「マーケティング5.0って何?【前編】誕生の理由や成功事例も紹介!」
「マーケティング5.0って何?【後編】マーケティング1.0から4.0をおさらい」
マーケティング1.0|製造中心のアプローチ
マーケティング1.0は1960年代~1990年代までさかのぼります。産業革命以降、大量生産・大量消費の流れが市場の中心でした。供給よりも需要が大きく、安ければ売れる時代です。企業は、自社製品を多くの消費者に安く提供し、利益を最大化させることを目指していました。
この時代のマーケティングは、製品そのものを分析するのが主流でした。消費者がどのような製品を求めているのかというよりも、企業が売りたい製品を売ることがメインです。
この時代に登場したマーケティングのフレームワークが「4P分析」です。これは、Product(製品・サービス)、Price(価格・料金)、Place(流通・店舗)、Promotion(販促・広告)の頭文字を取ったもので、現代でも活用されています。
4P分析についてより詳しく知りたい方は、下記の記事も合わせて参考にしてください。
「4P分析とは?分析を進める手法と押さえておくべきポイントを解説」
マーケティング2.0|消費者志向のアプローチ
マーケティング2.0は1970年代~1980年代を指します。マーケティング1.0時代に消費者の生活は豊かになりましたが、オイルショックなどが起こり、経済は混乱状態にありました。
加えて、技術革新により同じ製品が安価で製造できるようになったため、企業同士の価格競争が激化していきます。そうした流れのなか、製品を大量に安く提供するだけでは、消費者の関心を引くことが難しくなっていきました。
そこで、マーケティング2.0では、消費者のニーズを考慮した製品やサービスが売れるようになります。作り手主導から買い手主導の市場へと変わり、企業は消費者のニーズを満たす製品づくりを重視するようになったのです。
また、この時代には「STP分析」というフレームワークが誕生しました。これは、Segmentation(市場の細分化)、Targeting(ターゲット市場の選定)、Positioning(製品・ブランドの位置づけ)の3つの分析を行うもので、現在でも活用されています。
STP分析についてさらに詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
「STP分析で得られるメリットとは。やり方と実施時の注意点を解説」
マーケティング3.0|価値観・社会的要素を重視したアプローチ
マーケティング3.0は1990年代~2000年代初頭の時代です。インターネットの普及によって消費者が自ら情報を得られるようになり、モノで溢れた市場のなかで企業間の競争がさらに激化していきました。
消費者の価値観が多様化し、製品のほかにも、企業の社会的責任やブランドが提供する価値観が重視されるようになります。消費者が、製品の良さ以外にも、作り手の倫理観や環境問題への姿勢を見て購入する製品を選ぶ時代です。
この時代の新しいフレームワークはありませんが、企業の社会的責任(CSR)が強く求められてきました。
マーケティング4.0|デジタル技術を活用したアプローチ
マーケティング4.0は2010年代のマーケティングを指します。インターネットとソーシャルメディアが急速に普及し、消費者の買い物に対する意識が大きく変わり始めました。オンラインでの買い物が台頭し始めたため、オフラインとの連携による細かいマーケティングが求められた時代です。
マーケティング4.0にも特定のフレームワークはありませんが、オムニチャネル戦略やデジタルマーケティングが重要なポイントでした。この時代の消費者は、コミュニケーションを重視する傾向にありました。デジタルチャネルを通してリアルタイムでコミュニケーションをとるのが一般的になった時代でもあります。
デジタルマーケティングについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
「【初心者の方必見!】デジタルマーケティングの基礎知識を紹介」
マーケティング5.0|AIとテクノロジーを活用したアプローチ
マーケティング5.0は、2020年代から現代のマーケティングを指します。IoTやAI、ビッグデータなど、技術革新が進んでいます。消費者1人1人の満足度を向上させる取組が求められているところです。
現代は特に新しいフレームワークはありませんが、マーケティングの自動化やインタラクティブな体験など、テクノロジーを駆使したマーケティングが重要です。デジタルにあふれる社会のなかで、より消費者の人間性を重視した個別の対応が企業に求められています。
人工知能とマーケティングについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。
「人工知能(AI)で未来はどう変わる?人工知能の現状と予測される変化」

【6ステップ】マーケティング活動の基本的な流れ
マーケティング活動は具体的にどのようなことをするのでしょうか。ここでは、マーケティング活動の基本的な流れについて6つのステップで紹介します。
1.マーケティング目標の設定
マーケティング活動を始める前に、目指すべき目標を明確に設定することが重要です。目標の例として、売上増やブランド力の向上、新規顧客の獲得などがあげられます。ざっくりとした目標だけでなく、数値目標や期日も決めておくことで、効果測定がしやすくなります。
2.ターゲットの設定(ターゲティング)
目標を決めたら、次にターゲットの設定をします。どのような人に自社製品を使ってほしいのか、ターゲット像を具体的に選定しましょう。ターゲットの選定は、その層のニーズや消費行動を分析し、より的確にアプローチする方法を導き出すために欠かせません。
ターゲティングの方法やフレームワークの使い方については下記の記事を参考にしてください。
「ターゲティングとは?メリットや設定方法・役立つフレームワークを紹介」
3.市場調査
ターゲティングの次は市場調査に移ります。消費者が何を求めているか、社会に何が必要なのかを把握して製品やサービスに反映することで、消費者の関心が得られます。市場調査では、定量的なデータと定性的なデータの両方が必要です。
調査方法は、アンケートやインタビューなど製品やサービスのジャンルを考慮して行いましょう。統計データなども役に立ちます。調査結果や統計データを分析して、消費者のニーズやトレンドを把握することが大切です。
市場調査について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
「市場調査とマーケティングリサーチの違いとは」
4.マーケティング戦略の設計
市場調査を終えたら、得られた情報をもとに製品やサービスの大枠と売り方を検討する必要があります。提供方法や参入する市場、金額設定の方針などを具体的に考えましょう。
マーケティングの歴史の中で重要視されてきた3C分析や4P分析、STP分析などのフレームワークを活用し、戦略を練ることが求められます。顧客満足度を維持しつつ利益を最大化する戦略を立案し、競合他社に対して優位性のある施策を打ち出しましょう。

5.マーケティング活動の実施
戦略や方向性が決まったら、いよいよマーケティング活動の実施に移ります。製品・サービスの企画とプロモーションを実施しましょう。
まず製品・サービスの企画では、具体的な名称や用途、金額を決定し、市場に売り出すために開発を行います。プロモーション活動では、製品やサービスをターゲットに売り込み、関心をもってもらうように働きかけましょう。
マーケティング活動では、消費者だけでなく、従業員、株主などの利害関係者すべてに価値を提供することが大切です。「三方よし」のマーケティング活動を行うことが成功のポイントともいえます。
6.評価・改善
マーケティング活動を行ったあとは、次回に活かすために効果測定が必要です。マーケティングの結果や成果をKPI(重要業績評価指標)で測定しましょう。
測定後に評価を行い、今回の課題を抽出します。次回により良いマーケティング活動ができるよう課題を改善する方法を検討しましょう。ここまで終わればマーケティング活動は一区切りです。
課題を活かしてまたマーケティング活動を計画し、実行するPDCAサイクルを回しましょう。継続してマーケティング活動を行うことで、ノウハウを蓄積しながら効果的なプロモーションを続けることができるようになります。
まとめ
マーケティングの定義は、時代の移り変わりとともに新たなものが提唱されてきました。企業主体のマーケティングから消費者や社会が主体となるマーケティングに変わっており、今後もその傾向は続くと考えられます。
マーケティング活動を続ける上で、消費者の心理やトレンドを敏感にキャッチし、戦略に活かすことが、利益の最大化につながります。すべての利害関係者に価値を提供するマーケティング活動を展開しながら、競争優位性を築きましょう。
関連ページ