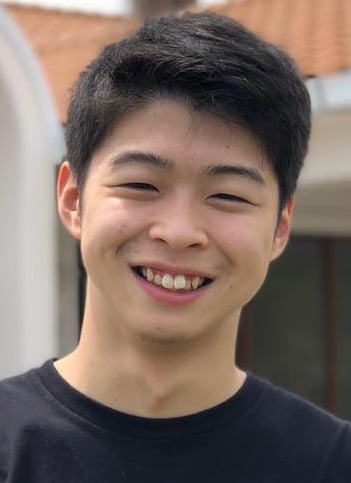インサイトスコープ
マーケティングリサーチャーの目線第3回 ビッグデータ時代におけるリサーチャーの役割とは
最終更新日:
公開日:
公開日:


TOTO
マーケティング マーケティング企画グループ 企画主査
小代 禎彦
1980年代前半ごろまで、マーケティングリサーチと言えば「質問紙調査」が主な手法でした。もちろんグループインタビューのような定性的な手法も用いられていましたが、実施件数で言えば圧倒的にアンケート調査であったと思います。そのアウトプットは、単純集計やクロス集計、およびこうしたデータのグラフが主流だったように思います。
拡大するマーケティングリサーチの守備範囲
 80年代後半に入ると、パーソナルコンピューターの普及によって、多変量解析が比較的手軽に行えるようになったためか、5件法や7件法の意識尺度を因子分析し、そのスコアを用いてクラスタ分析を行うといった手法も広く使われるようになってきました。最近では、こうしたレガシーな統計手法に加えて、構造方程式モデリング(SEM)や潜在クラス分析、階層ベイズを用いた手法など様々な統計手法が使われるようになっています。
80年代後半に入ると、パーソナルコンピューターの普及によって、多変量解析が比較的手軽に行えるようになったためか、5件法や7件法の意識尺度を因子分析し、そのスコアを用いてクラスタ分析を行うといった手法も広く使われるようになってきました。最近では、こうしたレガシーな統計手法に加えて、構造方程式モデリング(SEM)や潜在クラス分析、階層ベイズを用いた手法など様々な統計手法が使われるようになっています。定性調査も、インターネットを使ったWebグループインタビューやMROCのようなものも浸透してきました。さらには脳波やfMRIを用いた実験調査なども行われており、リサーチャーとして心得ておかなければならない守備範囲がとてつもなく広がっているように感じています。
取り扱うデータを考えてみても、アンケート調査のデータ一辺倒の時代から、テキストマイニングやPOSデータの分析などこちらも幅が広がって来ました。そして、ビッグデータと言う言葉を耳にしない日はない、という昨今です。ICTの急激な進歩によって、自然発生的に、しかも莫大な量のデータが日々蓄積されるようになると、こうしたデータを活用しない手はないとばかりに様々な関連ビジネスが沸き起こってきて、大きな時代の潮流を感じます。こうしたデータへの対応力も、リサーチャーに求められるようになってきており、調査手法の進化の過程と同時に歩みながら順を追って学んでこられた者とは異なり、これからスタートするリサーチャーにどこまでをどうやって身につけてもらうか、人材育成は頭の痛いことの一つでもあります。
ビッグデータの落とし穴
 Googleのエコノミストであるハル・バリアン氏が、「次の10年で最もSEXYな職業は統計家である」と述べ、西内啓氏の「統計学が最強の学問である」という本が注目されるなど、日本でも一大「統計学」ブームが沸き起こっています。また文部科学省も学習指導要領の改訂を行い、データに対する見方、考え方、処理の仕方といった統計教育の底上げにやっと取り組むようになったことは、喜ぶべきことと考えています。
Googleのエコノミストであるハル・バリアン氏が、「次の10年で最もSEXYな職業は統計家である」と述べ、西内啓氏の「統計学が最強の学問である」という本が注目されるなど、日本でも一大「統計学」ブームが沸き起こっています。また文部科学省も学習指導要領の改訂を行い、データに対する見方、考え方、処理の仕方といった統計教育の底上げにやっと取り組むようになったことは、喜ぶべきことと考えています。一方で、昨今のビッグデータブームをみると、とても違和感を覚えるところがあります。統計的な立場でのリサーチは、データをどうやって収集するかにとことんこだわります。誰を対象にどのような方法で、どのような仮説検証ができるかということを考えながら調査設計をするのが非常に重要です。
たとえば、若者をターゲットにした商品が、どの程度若者に支持されているかを調べるのに、若者にだけアンケートを取ってもあまり意味がありません。中高年にも同じように聞いて、その差に有意差があればこの商品のポジショニングは成功していると言えるでしょう。若者からお年寄りまで、一様に支持されているとしたら、それはそれで喜ばしいことかもしれませんが、それではそもそものマーケティング仮説が外れている、ということにほかなりません。
ほかにも、パッケージのデザインを2種類用意しておいて、どちらが目を引くかというようなマーケティング実験や、マイノリティーターゲットを狙うのであれば、割付け調査でマジョリティとの比較をするなど、データを主体性を持って計画的に集めるとういことが重要と考えます。
しかし、ビッグデータは自然発生的に集まってきてしまったデータですから、そのデータがどのようにして蓄積されてきたかという背景をしっかりと把握した上で分析し解釈する必要があります。お客様相談室のWebサイトに寄せられた、ある製品に対するご意見・ご質問のデータがあったとして、それはその製品ユーザー全体を代表する声とみなしてよいでしょうか。あるいは、ある製品では年収が低いほど総購買金額が高い、という現象が発見できたとして、この製品は低所得者に支持されていると判断してよいのでしょうか。
このような例では、明らかに裏がありそうだと想像が付きやすいですが、すべての現象が経験則から意味解釈付けができるとは限りません。人間による意味づけは、えてして先入観に影響されやすいものですし、後付けでどのような解釈もこじつけることが可能です。場合によっては、自分に都合のよいデータだけを抜き出して結論を導く、ということも、悪く言えば出来てしまいます。
リサーチャーの今日的役割とは
ビッグデータ全盛の時代になればなるほど、かえって統計的知識・スキルを持つ人材がさらに求められるようになると私は考えています。「データはあるんだ、何とかしてくれ」。そういう要求が増えてくることは明らかでしょう。こんな時役に立つ統計的考え方からのもう一つの側面は「批判的にデータをみる」という点です。
前節でふれたように、データから取り出された一つの発見は、それがそのまま事実とは限りません。あらゆる解釈の可能性があるわけですから、これを批判的に吟味し、疑似相関や交互作用といったものの可能性を予測し検証することで、得られた知見の確度を高めることができます。このことは、エンタープライズソフトウエアを使って情報を可視化し、隠れたビジネスチャンスを発見できます、というような形式的な作業とは一線を画するものです。
データは自らは何も語りません。データに何かを語らせることができるとしたら、それは解析者が解釈し、代弁することでしかなしえません。何故こうしたデータ(現象)が発生したのか、という「真のデータ発生のメカニズム」へどこまで迫れるか。それがデータに対峙するときに最も大切なことだと私は考えています。