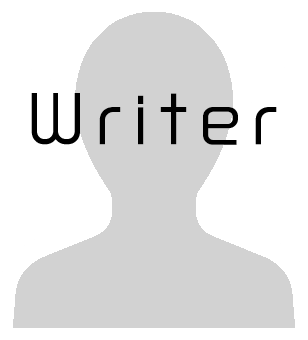ウェブアクセシビリティ義務化とは?法改正や対応するメリットを解説
公開日:

2024年4月1日から、障害者差別解消法の改正内容が適用され、民間事業者には「合理的配慮」が義務づけられています。Webサイトの場合ではウェブアクセシビリティを確保することがこれに該当します。今回は、ウェブアクセシビリティ義務化にかかわる法律や対応するメリット、具体例などを紹介します。
ウェブアクセシビリティとは
ウェブアクセシビリティとは、障がいの有無や年齢、利用環境などに左右されず、あらゆる人が快適にWebサイトを利用できる状態のことです。
現代社会では、インターネットが情報源のひとつとしての地位を確立しています。Webサイトへスムーズにアクセスできないと、必要な情報を得られなかったりサービスを利用できなくなったりすることもあります。
災害発生時など、緊急の場合にはWebサイトを利用できないことが命にかかわるかもしれません。そのため、どのような方でも利用しやすい、ウェブアクセシビリティに配慮したWebサイトの提供が求められています。
ユーザビリティの違いは?
アクセシビリティと混同されやすい言葉として「ユーザビリティ」がありますが、この2つの言葉には下記のような違いがあります。
・アクセシビリティ:誰でも情報を取得しやすい状態かどうか
・ユーザビリティ:ユーザーが使いやすいかどうか
良いWebサイトにするには、アクセシビリティとユーザビリティの両方に配慮する必要があります。
ウェブアクセシビリティの具体例
ウェブアクセシビリティを実現するには、障がいなどを抱えている方に配慮し、誰でもわかりやすいWebコンテンツを作ることが大切です。
ここでは、ウェブアクセシビリティの具体例を紹介しましょう。
出典:デジタル庁「Webアクセシビリティ導入ガイドブック」
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/08ed88e1-d622-43cb-900b-84957ab87826/60b7f8b0/20231110_introduction_to_weba11y.pdf
字幕や手話通訳
聴覚障がいがある方は、動画コンテンツで何を話しているのかが把握できません。そのため、字幕を付けたり、手話通訳を提供したりする必要があります。
コンテンツのわかりやすさ
文字色と背景色が似ていると、文字が背景に溶け込んで見えづらくなります。コントラストをはっきりさせて、見やすさを向上させることが大切です。また、視覚障がいがあるなどの理由から音声で情報を得る方のために、画像に代替テキストを設定して音声読み上げソフトを設置するのもウェブアクセシビリティの一環です。
互換性の確保
ユーザーによってPCやスマートフォン、タブレットなどWebサイト閲覧時の使用デバイスが異なります。どのデバイスからでもアクセスできるように、互換性を確保しておきましょう。
明確な指示とエラーメッセージの提示
例えばフォーム入力で、入力方法や間違えた箇所などがわからないと不便です。ユーザーが何をすべきなのか明確な指示を記載しておく、誤りがあった場合はわかりやすいエラーメッセージが提示されるようにするなどの配慮も求められます。
定期的なテストと更新
市場の動向や法改正などによって、ユーザーのニーズは刻々と変化します。また、配慮が不足している箇所が残っている場合もあります。定期的にWebサイトのテストを実施し、問題がある場合は内容を更新しましょう。

ウェブアクセシビリティ義務化の背景と影響
ウェブアクセシビリティは、すべての人が支障なくWebコンテンツを利用できることを意味します。ここでは、ウェブアクセシビリティが強く求められるきっかけとなった法改正と、義務化による影響について解説します。
障害者差別解消法とは
ウェブアクセシビリティは、「障害者差別解消法」の改正によってクローズアップされました。
障害者差別解消法は、障がいがある方への差別をなくし、すべての人々がお互いに尊重し合って共生する社会をつくる目的で2016年4月に施行されました。理想の社会実現のため、下記の3つが明示されています。
・不当な差別的取り扱いの禁止
・合理的配慮の提供
・環境の整備
上記のうち「合理的配慮の提供」は、対面はもちろんオンラインのサービスにも求められるものです。そのため、Webサイトで情報を提供している全事業者にとって、ウェブアクセシビリティの確保は取り組むべき社会的責任となったのです。
障害者差別解消法の法改正内容
障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」については、民間事業者は努力義務とされていました。しかし、2021年5月に行われた法改正によって完全義務化が決定され、2024年4月1日に施行されました。
ただし「合理的配慮の提供」とは、障がいのある方の生活を妨げるものを公的機関と民間事業者ができる限り取り除くことであり、求められるものすべてを提供するよう強制するものではありません。
そのため、ウェブアクセシビリティについても、上記で紹介した内容をすべて実現しなければならないというわけではないのです。なお、障害者差別解消法の「不当な差別的取り扱いの禁止」は義務、「環境の整備」は努力義務とされています。
義務化による影響は?罰則はある?
先述の通り、「合理的配慮の提供」が義務化されたとはいえ、「民間事業者ができる範囲で」という条件がついています。スキルや金銭的な問題などから実現できない可能性もあるため、現時点ではウェブアクセシビリティに対応しきれなくても罰則が科されることはありません。
ただし、努力した形跡もなく放置していると、行政から指導や勧告を受けたり、民事訴訟に発展したりするリスクがあります。

ウェブアクセシビリティを改善するメリット
ウェブアクセシビリティの改善への注力は、企業にさまざまなメリットをもたらします。どのようなメリットが得られるのか、具体的な内容を紹介します。
会社のイメージアップにつながる
ウェブアクセシビリティを高める取り組みは、企業のイメージアップに役立ちます。ウェブアクセシビリティに対応することは、事業者が社会的責任を果たしているとみなされるためです。
罰則がないからと何もせずに放置する企業より、少しでも対応しようと努力している企業のほうが良心的だと思う人は多いはずです。こうした積み重ねが企業の信頼性やブランド価値向上につながります。
より多くのユーザーに利用してもらえる
ウェブアクセシビリティに配慮したWebサイトは、ユーザーの属性や使用デバイスなどにかかわらず誰にとっても使いやすいため、利用者が増加しやすいというメリットもあります。
アクセスが容易で、音声読み上げ機能や画面拡大機能などもあれば、補助機能を利用しているユーザーも満足できるでしょう。画面にタッチできなかったり、周囲が騒がしかったりするときでも快適に使えるような設計は可能です。
SEO効果が見込める
ウェブアクセシビリティを向上させれば、SEO効果が高まる効果も期待できます。ウェブアクセシビリティに対応したサイトにすると、検索エンジンが評価する構造化データやaltタグ(画像の代替となるテキスト情報)の活用につながるためです。
また、ページの構造がシンプルで明確になるので、検索エンジンにとって理解しやすくなり、インデックスされやすくなります。「インデックスされない=検索エンジンに認識されない」ということであり、どれだけ対策を講じてもSEOの効果が得られません。ウェブアクセシビリティに配慮すれば、自然にクローラーにも配慮したWebサイトになるので、その後の施策の効果が出やすくなります。
まとめ
「ウェブアクセシビリティの義務化」といわれますが、正確には障害者差別解消法の「合理的配慮の提供」の義務化です。合理的配慮はあくまでも事業者が可能な範囲で対応することを求めるものなので、ウェブアクセシビリティに対応できていなくても罰則を科されることはありません。
ただし、一切何もせずに放置していると行政から指導や勧告を受けたり民事訴訟に発展したりする可能性があるため注意が必要です。ウェブアクセシビリティに取り組むことには、企業イメージが向上する、SEO効果が見込めるなどいろいろなメリットがあります。放置せずに取り組んでみてはいかがでしょうか。