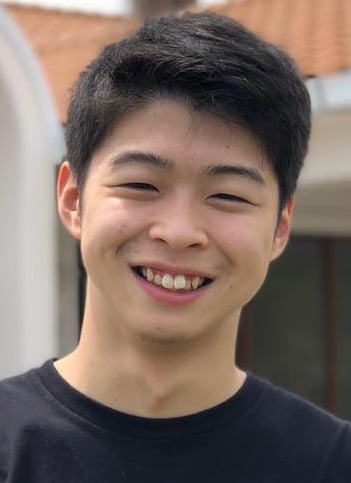デジタルマーケティングコラム
デジタル広告は昔と何が変わった?~1990年代後半からの広告トレンド振り返り~
最終更新日:
公開日:
公開日:

前回は、2021年のデジタル広告のトレンドを振り返りましたが( 前回のコラムはこちら)、今回は日本で初めてデジタル広告が登場した1990年代中頃から現在までどのようにトレンドが変化したのかまとめました。最近では動画広告やソーシャルメディア広告、モバイル広告など、デジタル広告の種類が随分と増えました。しかし変化したのは広告の種類だけではありません。プライバシーへの配慮や配信内容の健全性など、デジタル広告のあり方そのものが変わりつつあります。過去のトレンドを踏まえた上で、2022年以降はどのような点を意識すれば良いのかを探っていきましょう。
年代毎の振り返り
デジタル広告の今と昔について、過去のトレンドを振り返ってみます。どのような変遷を経て現在のトレンドが形成されたのか、以下で詳しく解説します。2000年以前
日本でデジタル広告が誕生したのは1996年。検索サイトYahoo!JAPANがバナー広告をリリースしたことがきっかけです。その後、gooやInfoseekといった検索サイトを筆頭に、朝日新聞や日本経済新聞などのWebサイトがバナー広告の提供を開始しました。同じ頃にメールマガジン発行サービスが生まれたことで、メール広告のサービスもスタートしています。1996年にはAmazonが「アソシエイトプログラム」の提供を始めました。これは世界初のアフィリエイトプログラムで、1999年には日本にもその仕組みが上陸しています。例えば1999年にサービスを開始したValue Commerceや翌年に登場したA8など、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)と呼ばれるサービスが誕生しました。

2000年代
2000年になるまではバナー広告やメール広告が主流でしたが、2000年代に入るとより高度なシステムを用いたデジタル広告が生まれました。その一つが検索連動型広告です。2002年には、日米で「Google Adwords(現Google広告)」や「Overture(現Yahoo!JAPAN広告)」のサービスがスタート。少額予算から広告を出すことができることや、効率良く消費者にアプローチできることから、当時は「もっとも優れた広告」とまで言われていました。
2003年になるとGoogleやOvertureがコンテンツ連動型広告を提供し始めます。パブリッシャーの膨大なメディアネットワークに広告を配信できる他、Webサイトのコンテンツやテーマを分析した上で最適な内容の広告を表示させる仕組みです。
Cookieに保管されているユーザー情報をデジタル広告に活用し始めたのは、2005年頃からです。そこからユーザーの検索・閲覧履歴に基づいて広告を表示できる、「行動ターゲティング」という仕組みが生まれました。行動ターゲティングの仕組みはさらに発展し、2008年には興味関心連動型広告というサービスが誕生しています。
2010年代
2010年初頭には、「アドエクスチェンジ」という仕組みが生まれました。「アドエクスチェンジ」とは、広告枠をインプレッション単位で取引する方法です。これにより「どの媒体に広告を出稿するのか」から「いくらで広告を出すのか」へと、広告主の考え方が変化しました。アドエクスチェンジのうち、競合他社と入札額を競い合って広告枠を獲得する方法をリアルタイム入札と言います。さらに2012年には動画広告、2014年にはネイティブ広告と、年を経てデジタル広告の種類が拡大しました。それだけ2010年代は、消費者の価値観や消費行動に大きな変化が生まれたのだと言えます。
2022年以降の変化について
では、デジタル広告の今と昔を経たうえで、今後はどのような変化が現れるのでしょうか。ここでは2022年以降のデジタル広告のトレンドを予測します。プライバシー保護対策としてコンテキスト広告への期待が高まる
前回のコラムで、プライバシー保護の高まりによりGoogleやAppleが対応を急いでいることを説明しました。それはデジタル広告業界全体でも同じで、現在はコンテキスト広告に注力するといった対策が進められています。ユーザーが閲覧するページの情報をAIが解析し、好みや関心に合う広告を表示できるコンテキスト広告は、プライバシー保護の観点から大いに期待が高まっています。例えば最近では、「GumGum」や「Candy」など、主にコンテキスト広告を提供するサービス会社が増えてきました。
デジタル広告のなかでモバイル広告が主力に
数あるデジタル広告のなかでも、2022年以降はさらにモバイル広告の重要性が高まる可能性があります。デジタル広告のスコアリングサービスを提供するIntegral Ad Science(IAS)は、独自レポートの「The 2022 Industry Pulse Report」にて、モバイル広告の重要性を示唆しています。調査によるとメディア専門家の60%が、今後優先的にリソースを割くメディアに「モバイル」と回答しました。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000014440.html
また、パンデミックが収束し人々の外出が増えることで、モバイル広告への支出が10%増えることも予測しています。その結果、国内デジタル広告市場におけるモバイル広告の比率が4分の3を占めます。デジタルマーケティングと同様、広告分野でもモバイルに対する重要性がますます高まっていくことでしょう。

アドフラウドやビューアビリティに対する注目度が高まる
デジタル広告市場の拡大により、今後はさらにアドフラウドやビューアビリティへの注目度が高まる可能性があります。アドフラウドとは不正広告のことで、実際には効果のないインプレッションやクリックによって不正に広告費を請求する行為です。例えば、特定のWebページへのアクセスや広告のクリックを行うボットを使ってインプレッション数やクリック数を水増しされると、広告主は不正な成果に対しても料金を支払わなければなりません。
ビューアビリティとは広告が表示された回数の中で、実際にユーザーが閲覧できる状態にあったインプレッションの比率です。Webページの最下部に広告が表示されてしまうと、ユーザーが広告を見ずにページを離脱してしまう恐れがあります。しかしページが表示された時点でインプレッション分の課金が発生するため、アドフラウドのように無駄な広告表示にお金を払っていることになります。
先述したIASの調査によると、2022年におけるデジタル広告の最大の懸念事項として、アドフラウドが74%で1位となっています。またソーシャルメディア広告については、全体の54%の回答者がビューアビリティの対策が最優先だと答えています。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000014440.html
アドフラウドやビューアビリティの問題に対応するためには、広告がクリックされた後の成果を確認するだけではなく、広告が表示される段階の状況をチェックすることが重要です。こうした対策用のツールとして、最近はアドベリフィケーション(広告価値検証)ソフトが登場しています。
まとめ
デジタル広告は時代を経て、広告運用の目的や施策にも変遷がみられます。日本でデジタル広告が誕生した初期の2000年代では、ユーザーの検索・閲覧履歴などの行動特性に紐づき、いかに広告を効果的に表示できるかに注力した時代でした。2010年代以降になると、デジタル広告の種類も増え、ユーザーの情報特性に基づき、広告費用を効率的に運用できる仕組みも誕生しました。これからは、プライバシー侵害や広告価値棄損といった問題が表面化したことで、サードパーティCookieを活用しないターゲティング広告が求められます。個人情報が特定しづらい中で、いかに「それらしい」ユーザーセグメントを見つけ出し、どのように可視化していくのかが成果を上げるために重要になってきます。
デジタル広告の今と昔を比較することで、その時代に合った広告運用を意識してみましょう。
【参考URL】
https://www.shopowner-support.net/customer_attraction_information/web/trends-in-new-advertising-media/#chapter-16
https://marketing.creditsaison.jp/article/2021/06/14/104
https://digiday.jp/brands/seven-trends-that-will-shape-the-advertising-and-marketing-industry-in-2022/
https://integralads.com/jp/insider/industy-pulse-2021-japan/
https://dmlab.jp/web/history.html
https://www.tis.jp/special/marketingit/history_of_digitalmarketing/